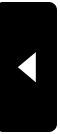2012年11月06日
炉開き
先日、お茶のお稽古をつけて頂いている先生茶室にて炉開きのお祝いに出席させて頂きました。
11月といえば’茶人の正月’とも言われ、炉開きが催され風呂から炉へと変わります。
5月に採れた碾茶を半年間熟成させ、11月の炉開きで使用します。
熟成させたお抹茶は、深みと旨みが増し言わば飲み頃になります。
三畳程の茶室で戴くお濃い茶は、静かな空気と自然の光、お墨のほのかな香り、お濃い茶を練る時のお抹茶の香り、御亭主のお気持ちとが調和されて、極上の一服になります。
心を落ち着かせて、日々のストレスから解放される癒しのひと時でした。
11月といえば’茶人の正月’とも言われ、炉開きが催され風呂から炉へと変わります。
5月に採れた碾茶を半年間熟成させ、11月の炉開きで使用します。
熟成させたお抹茶は、深みと旨みが増し言わば飲み頃になります。
三畳程の茶室で戴くお濃い茶は、静かな空気と自然の光、お墨のほのかな香り、お濃い茶を練る時のお抹茶の香り、御亭主のお気持ちとが調和されて、極上の一服になります。
心を落ち着かせて、日々のストレスから解放される癒しのひと時でした。
2012年10月08日
宇治茶まつり
先日、毎年恒例の宇治茶まつりが開催されました。
昭和7年より毎年10月第1日曜日の朝から終日、宇治川畔一帯で開催されます。 これは、初めてお茶を中国より日本に伝えた明庵栄西禅師と、宇治に茶園を開いた明恵上人、茶道の始祖千利休の三恩人への報恩感謝、かねては茶業功労者の遺績を追慕するとともに、宇治茶の隆盛を祈願するための行事です。
宇治茶祭の流れ↓
・ 名水汲み上げの儀 ↓
・茶壷口切の儀↓
・ 茶筅塚供養↓


今年は幣園から1名、名水汲み上げの儀に参加させていただきました。
昔、豊臣秀吉が宇治川の水を汲んで茶会を開いたことから、 宇治橋「三の間」からシュロ縄につるした釣瓶で清水を汲み上げ、 これを竹筒に移し、当時を想わせる衣装に身をつつんだ行列により、献茶の行われる右岸の興聖寺に大切に運びます。
行列によって名水が興聖寺本堂に運ばれると、「茶壷口切の儀」が行われます。 今年摘まれた新茶を入れ、この茶まつりの日まで封をし仏前に供えられていた茶壷の口を切り、 それを石臼で抹茶に仕上げ、汲み上げた三の間の名水を使ったお湯でお茶を点て、 茶祖に献茶し、栄西禅師開基の京都・建仁寺の読経がおこなわれます。
この「茶壷口切の儀」を観るために、毎年全国から多くの観光客や、 茶業を営む方が宇治に来られます。
「茶壷口切の儀」の式典後、興聖寺山門前の茶筅塚で、 使い古した茶筅の供養法要が営まれます。
こうして、ここ宇治では、70年以上にわたり、宇治茶の歴史における先人への感謝と、 これからの宇治茶のさらなる発展への祈願を込めて、毎年おごそかに行われております。
昭和7年より毎年10月第1日曜日の朝から終日、宇治川畔一帯で開催されます。 これは、初めてお茶を中国より日本に伝えた明庵栄西禅師と、宇治に茶園を開いた明恵上人、茶道の始祖千利休の三恩人への報恩感謝、かねては茶業功労者の遺績を追慕するとともに、宇治茶の隆盛を祈願するための行事です。
宇治茶祭の流れ↓
・ 名水汲み上げの儀 ↓
・茶壷口切の儀↓
・ 茶筅塚供養↓
今年は幣園から1名、名水汲み上げの儀に参加させていただきました。
昔、豊臣秀吉が宇治川の水を汲んで茶会を開いたことから、 宇治橋「三の間」からシュロ縄につるした釣瓶で清水を汲み上げ、 これを竹筒に移し、当時を想わせる衣装に身をつつんだ行列により、献茶の行われる右岸の興聖寺に大切に運びます。
行列によって名水が興聖寺本堂に運ばれると、「茶壷口切の儀」が行われます。 今年摘まれた新茶を入れ、この茶まつりの日まで封をし仏前に供えられていた茶壷の口を切り、 それを石臼で抹茶に仕上げ、汲み上げた三の間の名水を使ったお湯でお茶を点て、 茶祖に献茶し、栄西禅師開基の京都・建仁寺の読経がおこなわれます。
この「茶壷口切の儀」を観るために、毎年全国から多くの観光客や、 茶業を営む方が宇治に来られます。
「茶壷口切の儀」の式典後、興聖寺山門前の茶筅塚で、 使い古した茶筅の供養法要が営まれます。
こうして、ここ宇治では、70年以上にわたり、宇治茶の歴史における先人への感謝と、 これからの宇治茶のさらなる発展への祈願を込めて、毎年おごそかに行われております。
2012年09月09日
「てったいや」
先日、御来店下さったお客様とのお話です。
その方は、やけに茶作りにお詳しい御主人様でした。
私が、「茶業者の方ですか?」とお尋ねしたところ「俺は昔‘てったいや‘してたんや!」とおっしゃいました。
「てったいや」とは「手伝いさん」の訛りで、主にフリーの建築業助手のことで使われることが多いようですが、(上方落語に、てったいやのまたべえが登場しますね。)今回のお客様は、少し違った種類の「てったいや」さんです。
京都には、様々な特産品があります。代表的なのが宇治茶、伏見の酒、京野菜など…
今回の「てったいや」とは、その特産品収穫の最盛期にお手伝いをされに行く職業の方のことです。
春には乙訓(向日市や長岡京)にタケノコの収穫の手伝いに行き、5月に入ると宇治で茶作り仕事、(当時は製茶機械が無かったので、すべて手揉み茶)それを終えると、米の田植え仕事(これも当時は機械ではなく手で植えます)が待っています。
夏は野菜畑の手伝いや大工仕事をします。
秋は稲刈り(もちろん手作業)をし、終わるとすぐに冬が来ますので、伏見の酒蔵にこもり酒造りに励みます。
1年を通して様々な仕事をするてったいやさんは想像以上に器用な方でなければ務まりません。
幣園にも5月になると、てったいやさんが泊まり込みで来られていました。短い期間とはいえ、一晩中交代で手揉み茶製造をするのは、蒸し暑さと眠たさで「地獄の日々だった」とおっしゃっていました。
また、泊まり込み仕事で家を空けることが多かったので、家族には寂しい思いをさせた。ともおっしゃっていましたが、家族を想い一生懸命働く大黒柱の気持ち、そして父なしで家を守ってこられた奥様の絶え間ない御苦労を想像すると涙なしでは語れません。
素敵なお話を聞かせて頂きました。
その方は、やけに茶作りにお詳しい御主人様でした。
私が、「茶業者の方ですか?」とお尋ねしたところ「俺は昔‘てったいや‘してたんや!」とおっしゃいました。
「てったいや」とは「手伝いさん」の訛りで、主にフリーの建築業助手のことで使われることが多いようですが、(上方落語に、てったいやのまたべえが登場しますね。)今回のお客様は、少し違った種類の「てったいや」さんです。
京都には、様々な特産品があります。代表的なのが宇治茶、伏見の酒、京野菜など…
今回の「てったいや」とは、その特産品収穫の最盛期にお手伝いをされに行く職業の方のことです。
春には乙訓(向日市や長岡京)にタケノコの収穫の手伝いに行き、5月に入ると宇治で茶作り仕事、(当時は製茶機械が無かったので、すべて手揉み茶)それを終えると、米の田植え仕事(これも当時は機械ではなく手で植えます)が待っています。
夏は野菜畑の手伝いや大工仕事をします。
秋は稲刈り(もちろん手作業)をし、終わるとすぐに冬が来ますので、伏見の酒蔵にこもり酒造りに励みます。
1年を通して様々な仕事をするてったいやさんは想像以上に器用な方でなければ務まりません。
幣園にも5月になると、てったいやさんが泊まり込みで来られていました。短い期間とはいえ、一晩中交代で手揉み茶製造をするのは、蒸し暑さと眠たさで「地獄の日々だった」とおっしゃっていました。
また、泊まり込み仕事で家を空けることが多かったので、家族には寂しい思いをさせた。ともおっしゃっていましたが、家族を想い一生懸命働く大黒柱の気持ち、そして父なしで家を守ってこられた奥様の絶え間ない御苦労を想像すると涙なしでは語れません。
素敵なお話を聞かせて頂きました。
2012年08月18日
空中大和茶カフェ
2012年07月04日
日本茶愛飲家「ルーカスさん」

今日は、珍しいお客様が来て下さいました。
遠路遥々、オーストラリアから。
ルーカスさんはオーストラリアでレントゲン技師をなさっている28歳。
日本茶に大変興味があるようで、茶園と揉み茶工場見学には大変感心しておられました。
特に玉露がお好きなようで、甘みの強いお茶を好まれていました。
幣園自慢の「だんご茶」にも興味をもたれ、一粒そのまま食べて頂くと、、
さすがに濃厚な茶の香味にびっくりしておられました。笑
2012年06月18日
籠破り
幣園では6月7日に茶摘みを終え、約1ヵ月間の製茶作業を振り返りながら、茶摘みさんや職人の為に慰労会を開きます。その慰労会の事を、茶摘み籠を破ってお終いという意味から「籠破り」と言います。
茶摘み作業をしているときは、帽子を被ったりマスクをしている方が多いので、綺麗に着替えて籠破りに来られたお茶摘みさんは、いつもより綺麗に見えて誰だかわからなくなる方もいらっしゃいます。(笑)
年に一度のお茶摘み、年に一度の籠破り、最後を締めくくるに相応しい、それはもう盛大に飲んで食べてしゃべって笑っておお賑わいでした。
帰り際に、「また来年もよろしくお願いします」とこちらが言うと、「また来年会いましょう」言われるとなんだか少し寂しいですが、また一年しっかりお茶を育てていこう!という気持ちになります。
なにはともあれ、無事今年もおいしい新茶が採れたことにホッとしています。
茶摘み作業をしているときは、帽子を被ったりマスクをしている方が多いので、綺麗に着替えて籠破りに来られたお茶摘みさんは、いつもより綺麗に見えて誰だかわからなくなる方もいらっしゃいます。(笑)
年に一度のお茶摘み、年に一度の籠破り、最後を締めくくるに相応しい、それはもう盛大に飲んで食べてしゃべって笑っておお賑わいでした。
帰り際に、「また来年もよろしくお願いします」とこちらが言うと、「また来年会いましょう」言われるとなんだか少し寂しいですが、また一年しっかりお茶を育てていこう!という気持ちになります。
なにはともあれ、無事今年もおいしい新茶が採れたことにホッとしています。
2012年05月16日
茶摘み真っ盛り
幣園では5月8日から本年度の茶摘みを開始しました。
去年より二日早いスタートです。例年通り上質且つ安心安全な宇治茶作りに精進しております。
毎年、お茶摘みは年に一度の一大行事と言わんばかりに、たくさんの茶摘み娘さんが集まって下さいます。
遠くの方は京都市内や伏見区から宇治まで毎日通って、精を出して下さいます。
幣園がいつもお茶摘み娘さんに対して言わしてもらうこと。それは1年間大事に丁寧に育て実った茶葉を、最後に茶摘み娘さんに摘んで頂かなければ、宇治茶として市場に出すことができない。だから責任は重大です。
育てた側も摘んで頂く茶摘み娘さん側もお互いを尊重し合って、手摘みの宇治茶に誇りをもって作って行きましょう!!と伝えます。
大量生産やコスト削減により機械摘み茶園が増えている中、幣園は90%が手摘み茶園です。(残りは機械摘み茶園)手摘みの宇治茶や茶摘み文化を後世に継承するのも我々の使命だと考えています。
そんな気持ちを込めた宇治茶が今年も出来上がっています。どうぞ一度ご笑味下さい。。

去年より二日早いスタートです。例年通り上質且つ安心安全な宇治茶作りに精進しております。
毎年、お茶摘みは年に一度の一大行事と言わんばかりに、たくさんの茶摘み娘さんが集まって下さいます。
遠くの方は京都市内や伏見区から宇治まで毎日通って、精を出して下さいます。
幣園がいつもお茶摘み娘さんに対して言わしてもらうこと。それは1年間大事に丁寧に育て実った茶葉を、最後に茶摘み娘さんに摘んで頂かなければ、宇治茶として市場に出すことができない。だから責任は重大です。
育てた側も摘んで頂く茶摘み娘さん側もお互いを尊重し合って、手摘みの宇治茶に誇りをもって作って行きましょう!!と伝えます。
大量生産やコスト削減により機械摘み茶園が増えている中、幣園は90%が手摘み茶園です。(残りは機械摘み茶園)手摘みの宇治茶や茶摘み文化を後世に継承するのも我々の使命だと考えています。
そんな気持ちを込めた宇治茶が今年も出来上がっています。どうぞ一度ご笑味下さい。。

2012年04月05日
可愛らしい新芽
4月に入りましたが、なかなか気温が上がりませんね。
写真は3月31日の玉露園の新芽です。
「ちょこん」と可愛らしい新芽ですが、あと1ヶ月すればグンッと大きく成長し、美味しい宇治玉露になります。
お楽しみに♪♪
2012年03月16日
茶園の植え替え
2012年02月03日
春の宇治茶フェスタ
明日2月4日土曜日、宇治茶会館と京都府茶業センターに於いて、春の宇治茶フェスタが開催されます!!
宇治茶会館では宇治茶味めぐりや宇治茶を使った和菓子作りの体験教室、茶業センターでは、子供茶香服大会や宇治茶の秤売り等、盛りだくさんのイベントです!!
京阪宇治駅、JR宇治駅から無料シャトルバスが運行しておりますので是非ご利用になってお越しください!!
幣園からも宇治茶会館で行われる「宇治茶の産地めぐり、味めぐり」のお手伝いに行かせていただきます!!
たくさんの御来場お待ちしております☆
☆春の宇治茶フェスタ詳細☆
宇治茶会館では宇治茶味めぐりや宇治茶を使った和菓子作りの体験教室、茶業センターでは、子供茶香服大会や宇治茶の秤売り等、盛りだくさんのイベントです!!
京阪宇治駅、JR宇治駅から無料シャトルバスが運行しておりますので是非ご利用になってお越しください!!
幣園からも宇治茶会館で行われる「宇治茶の産地めぐり、味めぐり」のお手伝いに行かせていただきます!!
たくさんの御来場お待ちしております☆
☆春の宇治茶フェスタ詳細☆
2012年01月07日
あけましておめでとうございます!!
2011年12月02日
茶園と柿の木
早いものでもう師走に入りました。
幣茶園では、寒い冬を乗り越えるために秋肥料をたっぷり与えています。
茶園の横には柿の木やミカンの木も植えています。

近年、カラスが餌を求めて山から下りてきて、まず茶園に与えたニシンの魚肥料を食べた後、デザートにせっかく実った柿の実をほとんど突いて食べられてしまっていました。(カラスは賢い。。)
しかし今年はカラスが少なく例年以上に柿がたくさん採れ、お得意様に配ることができるくらいでした。
しかし、なぜカラスが減少したのか??
考えられることは、カラス山に餌が足りているのか、それとも何か自然現象の前兆なのか。。。。
詳しいことは分かりませんが、茶園と柿の木を荒らされないですむので嬉しいのですが、少し不安です。
話が少しずれますが、茶園と柿の木が関係する話を一つ。。
我々茶農家では「雀の葉隠れ」という言葉を使います。
新茶が採れる5月より少し前に、茶園にヨシズと藁で覆いをします。その覆いを被せるバロメーターに使う言葉です。
茶と柿の木は生育スピードが似ており、柿の木に雀が止まって、葉っぱで少し雀が見え隠れするくらいの葉の大きさになったら、ヨシズ覆いを始めます。そして雀が完全に隠れるくらい葉が大きくなったら、よしずの上から藁を振ります。柿の木の葉っぱが、茶園覆いをするバロメータになっているのです。
いよいよ寒さが本格的になって参りました。紅葉も今週で見ごろが終りだそうです。
写真は平等院鳳凰堂の紅葉です。

幣茶園では、寒い冬を乗り越えるために秋肥料をたっぷり与えています。
茶園の横には柿の木やミカンの木も植えています。

近年、カラスが餌を求めて山から下りてきて、まず茶園に与えたニシンの魚肥料を食べた後、デザートにせっかく実った柿の実をほとんど突いて食べられてしまっていました。(カラスは賢い。。)
しかし今年はカラスが少なく例年以上に柿がたくさん採れ、お得意様に配ることができるくらいでした。
しかし、なぜカラスが減少したのか??
考えられることは、カラス山に餌が足りているのか、それとも何か自然現象の前兆なのか。。。。
詳しいことは分かりませんが、茶園と柿の木を荒らされないですむので嬉しいのですが、少し不安です。
話が少しずれますが、茶園と柿の木が関係する話を一つ。。
我々茶農家では「雀の葉隠れ」という言葉を使います。
新茶が採れる5月より少し前に、茶園にヨシズと藁で覆いをします。その覆いを被せるバロメーターに使う言葉です。
茶と柿の木は生育スピードが似ており、柿の木に雀が止まって、葉っぱで少し雀が見え隠れするくらいの葉の大きさになったら、ヨシズ覆いを始めます。そして雀が完全に隠れるくらい葉が大きくなったら、よしずの上から藁を振ります。柿の木の葉っぱが、茶園覆いをするバロメータになっているのです。
いよいよ寒さが本格的になって参りました。紅葉も今週で見ごろが終りだそうです。
写真は平等院鳳凰堂の紅葉です。

2011年11月24日
口切りの茶事
先日、いつもお茶のお稽古で御一緒させて頂いている方にご招待頂き、「口切りの茶事」に参加させて頂きました。
11月になると炉の季節・・・お茶の世界ではお正月にあたるこの時期、非常に格式の高いお茶事です。
「口切りの茶事」とは、春に取れた新茶を茶壷に封じて半年寝かせて11月に茶壷の封を切ります。茶壺に入れ半年間、寝かされた碾茶(碾茶を石臼で挽くと抹茶になります)3種類(5種類の時もあるそうです)からご亭主がお客様にどのお茶を飲みたいのか伺います。お客が指定したお茶を石臼で挽き、濃い茶として出します。
口切茶事順序
≪席入り→口切りの儀式→初炭→懐石→仲立ち→濃い茶→後炭→薄茶→退席≫となります。一部分しか写真撮影できず申し訳ありません。
御茶入日記(茶壺に入っているお茶の説明書き)
この中から頂きたいお茶を選択します。

茶壺の拝見

いよいよ口切りの儀式

初炭

石臼挽き

壺飾り

濃い茶点前

お茶人さんでもなかなか体験できない「口切りの茶事」です。
貴重な体験をさせて頂き、大変勉強になりました。
11月になると炉の季節・・・お茶の世界ではお正月にあたるこの時期、非常に格式の高いお茶事です。
「口切りの茶事」とは、春に取れた新茶を茶壷に封じて半年寝かせて11月に茶壷の封を切ります。茶壺に入れ半年間、寝かされた碾茶(碾茶を石臼で挽くと抹茶になります)3種類(5種類の時もあるそうです)からご亭主がお客様にどのお茶を飲みたいのか伺います。お客が指定したお茶を石臼で挽き、濃い茶として出します。
口切茶事順序
≪席入り→口切りの儀式→初炭→懐石→仲立ち→濃い茶→後炭→薄茶→退席≫となります。一部分しか写真撮影できず申し訳ありません。
御茶入日記(茶壺に入っているお茶の説明書き)
この中から頂きたいお茶を選択します。

茶壺の拝見

いよいよ口切りの儀式

初炭

石臼挽き

壺飾り

濃い茶点前

お茶人さんでもなかなか体験できない「口切りの茶事」です。
貴重な体験をさせて頂き、大変勉強になりました。
2011年10月14日
新米!秋の稲刈り
こんにちは。だいぶ秋めいてまいりましたね。。
幣園では少しお米も耕作しており、只今稲刈り作業を行っております。
稲刈りなんて機械(コンバイン)で刈ってしまえば終わりじゃないかと思われる方もいますが、幣園では茶園に使う藁が必要なため、昔ながらの「はさ掛け」をしてお米を作ります。

実りの秋

稲刈り機

刈り機がこのように稲(はさ)を結束します。

丸太と竹で棚を作ります。

一つ一つ人力ではさを棚に掛けていきます。

完成
このようにして出来た稲はさを10日ほど天日干しにしてから脱穀します。天日干しされたお米は旨味が増すともいわれております。
脱穀した後、藁を集め茶園の敷き藁にしたり、玉露や碾茶(抹茶原料)を作る時に本簾(ほんず)栽培を行う時のヨシズの上に拭く藁に使います。
お茶栽培にとって、お米作りも重要な役割を成しております。
幣園では少しお米も耕作しており、只今稲刈り作業を行っております。
稲刈りなんて機械(コンバイン)で刈ってしまえば終わりじゃないかと思われる方もいますが、幣園では茶園に使う藁が必要なため、昔ながらの「はさ掛け」をしてお米を作ります。

実りの秋

稲刈り機

刈り機がこのように稲(はさ)を結束します。

丸太と竹で棚を作ります。

一つ一つ人力ではさを棚に掛けていきます。

完成
このようにして出来た稲はさを10日ほど天日干しにしてから脱穀します。天日干しされたお米は旨味が増すともいわれております。
脱穀した後、藁を集め茶園の敷き藁にしたり、玉露や碾茶(抹茶原料)を作る時に本簾(ほんず)栽培を行う時のヨシズの上に拭く藁に使います。
お茶栽培にとって、お米作りも重要な役割を成しております。
2011年09月24日
お彼岸総供養大施餓鬼in大徳寺
2011年09月11日
新天地を求めた京焼~清水団地50年の歩み~

京都文化博物館において「新天地を求めた京焼展 清水焼団地五十年の歩み」が開催されております。
京都では豊かな工芸品がつくられてきました。その優れた意匠と高い技術を育む伝統は今日まで受け継がれています。
清水焼団地が50周年を迎えるのを機に、同所で活躍する他分野の作家の作品や清水団地の歴史や未来へむけての取り組みについて紹介されています。
9月19日敬老の日まで開催されていますので是非!!
http://www.bunpaku.or.jp/exhi_sogo3f.html
2011年08月12日
夏の茶園
毎日暑いですね。。
まあ夏なのでしょうがないですが、ここ最近異常な暑さを感じます。
我々人間が感じていると同様に、茶園はずっと太陽の光を浴びて生きているわけですから、もっと暑いはずです。。
春が過ぎ新茶の季節が終わると、茶園はどのような状態になっているかといいますと、、、
夏は茶葉や番刈りした後の枝の切断面から病害虫にとりつかれやすく、雑草は抜いても抜いても生えてきます。この時期にしっかりと病害虫や雑草をとり除かないと来年の新茶に大きく悪影響を及ぼします。。
なので生産家はどんな暑い日でも毎日、朝昼晩と茶園に行き、葉や枝の様子をチェックしに行きます。
日照りが続くと人工的に水もやります。私の父が最近よく言うのが、「昔はもっと夕立が降ったもんや。昼は晴れてもしっかり夕立が降ってくれると茶園が喜ぶんや。」と。
自然相手の商売ですので一筋縄ではいきません。
どの業界にも言えることですが、時代や流行にあったやり方が必要な昨今、農業も昔と現在では気候がだいぶ変ってきていますので、その時代に合った手入れも必要になってきています。

まあ夏なのでしょうがないですが、ここ最近異常な暑さを感じます。
我々人間が感じていると同様に、茶園はずっと太陽の光を浴びて生きているわけですから、もっと暑いはずです。。
春が過ぎ新茶の季節が終わると、茶園はどのような状態になっているかといいますと、、、
夏は茶葉や番刈りした後の枝の切断面から病害虫にとりつかれやすく、雑草は抜いても抜いても生えてきます。この時期にしっかりと病害虫や雑草をとり除かないと来年の新茶に大きく悪影響を及ぼします。。
なので生産家はどんな暑い日でも毎日、朝昼晩と茶園に行き、葉や枝の様子をチェックしに行きます。
日照りが続くと人工的に水もやります。私の父が最近よく言うのが、「昔はもっと夕立が降ったもんや。昼は晴れてもしっかり夕立が降ってくれると茶園が喜ぶんや。」と。
自然相手の商売ですので一筋縄ではいきません。
どの業界にも言えることですが、時代や流行にあったやり方が必要な昨今、農業も昔と現在では気候がだいぶ変ってきていますので、その時代に合った手入れも必要になってきています。